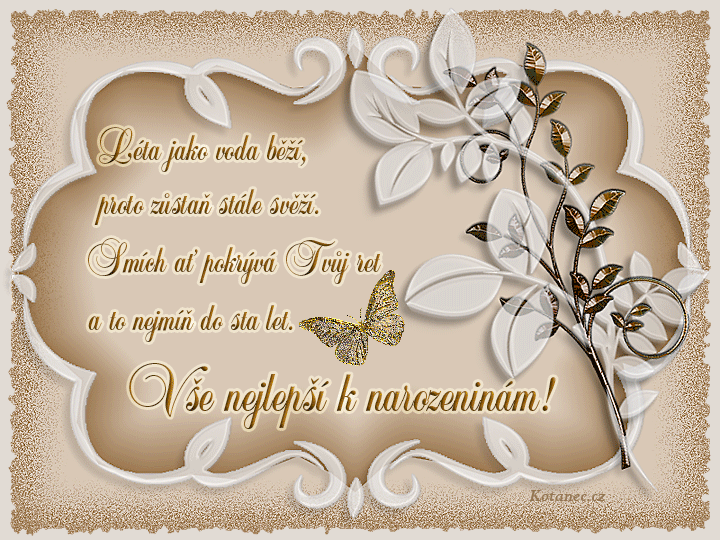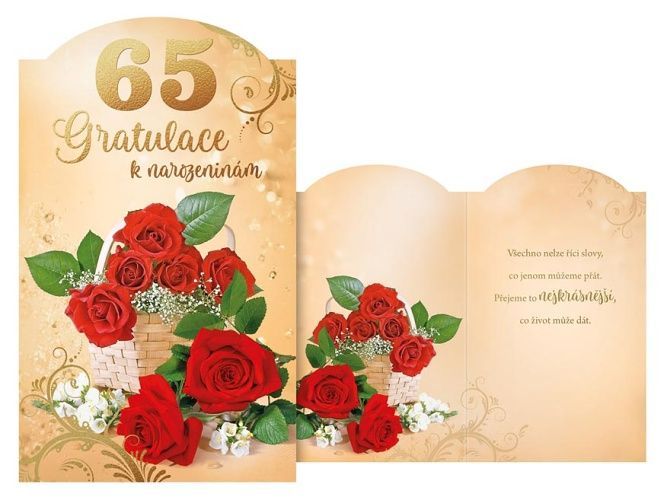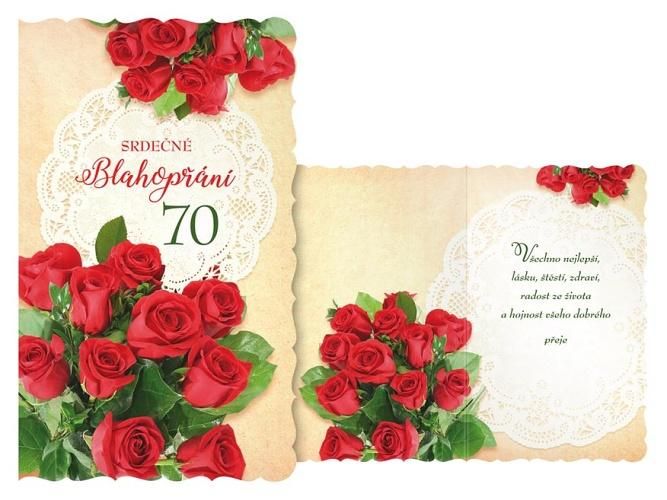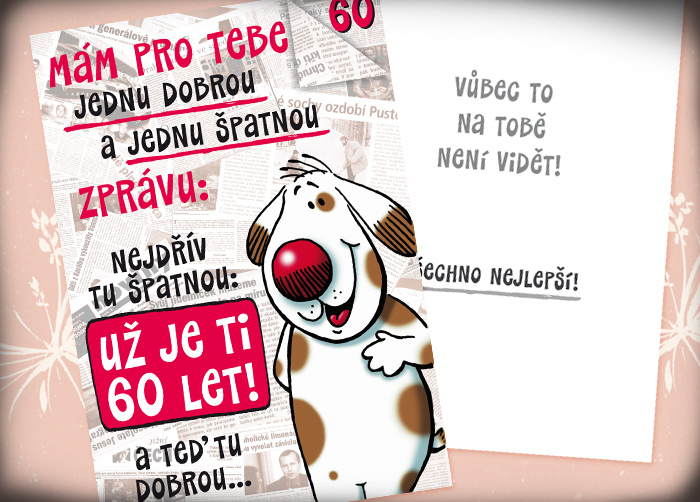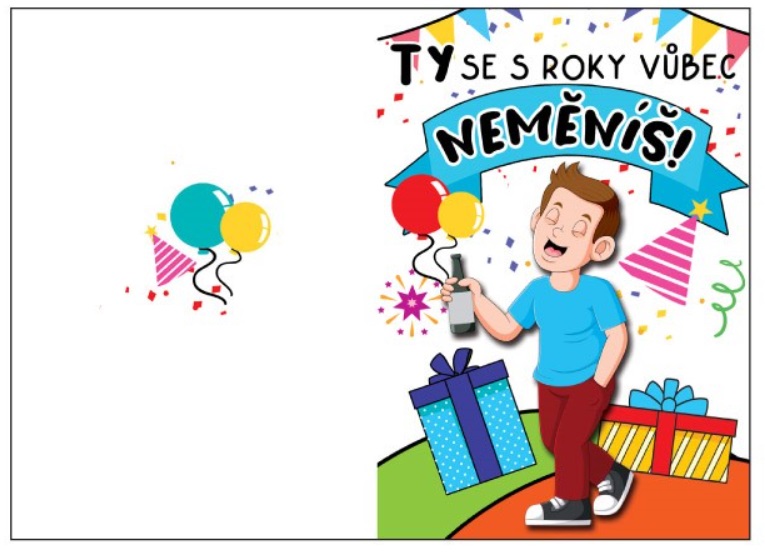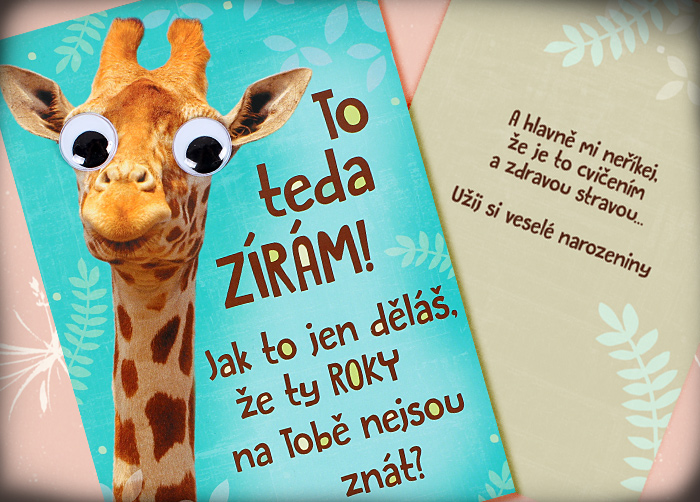Přání k narozeninám | Obrázky, animace, gify | Birthday gif, Table decorations, Happy birthday quotes

Rukodělný kroužek a ruční práce *online* - Papírové přání k narozeninám, ke dni matek, k Valentýnu - YouTube
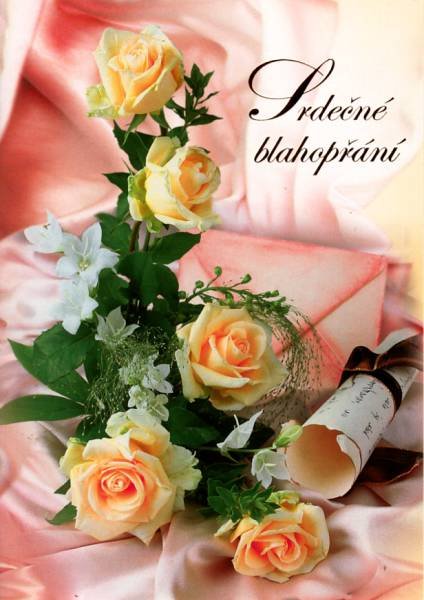
Elektronické pohlednice a obrázky k Narozeninám | strana-1 | Textová přáníčka, blahopřáníčka a citáty | www.blahopranicka.cz

Elektronické pohlednice a obrázky k Narozeninám | strana-1 | Textová přáníčka, blahopřáníčka a citáty | www.blahopranicka.cz