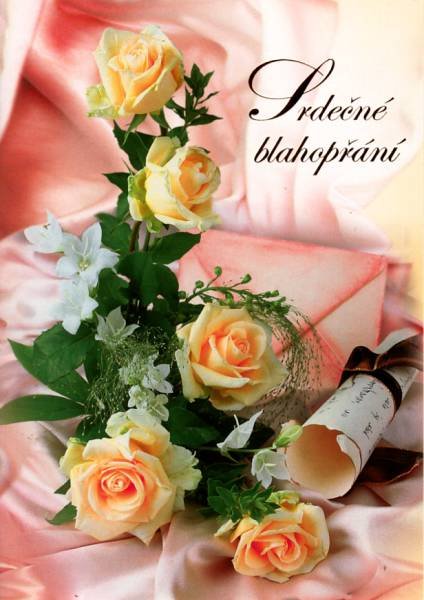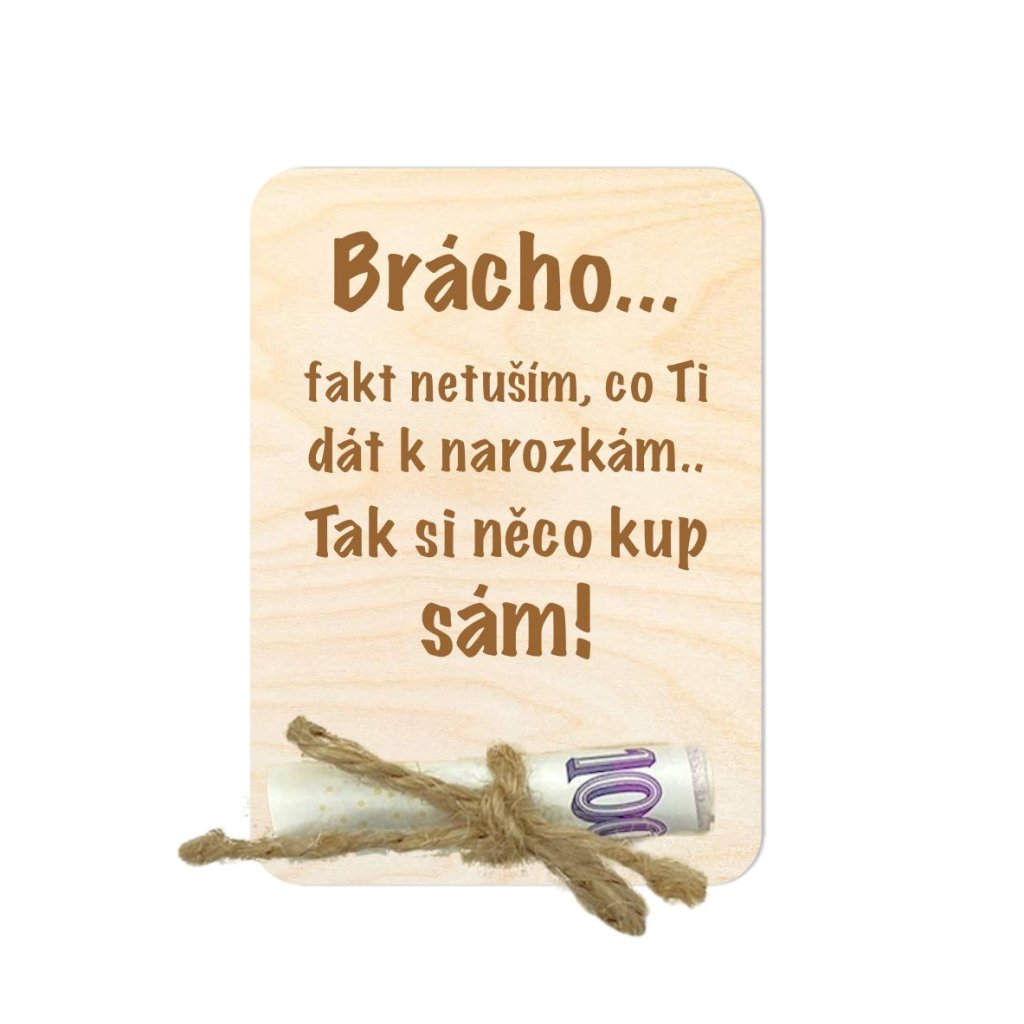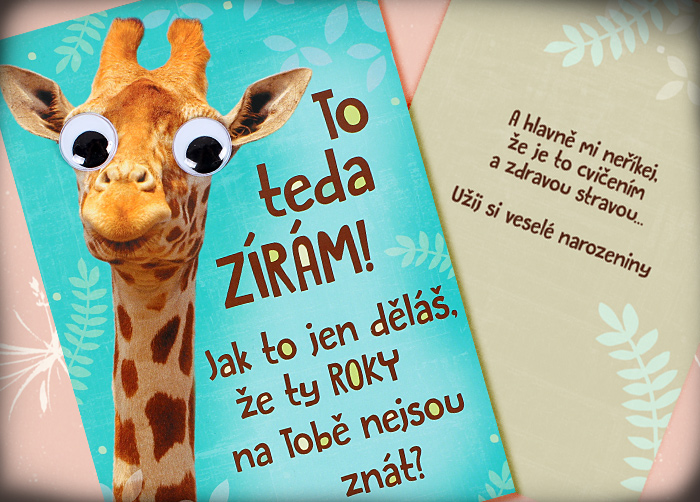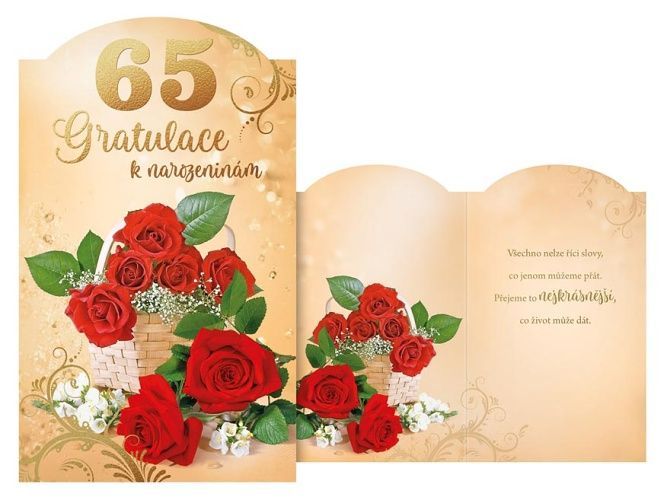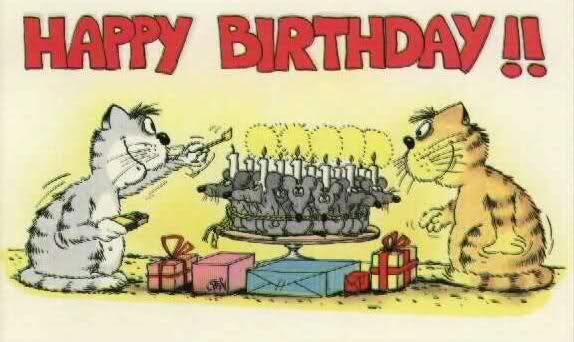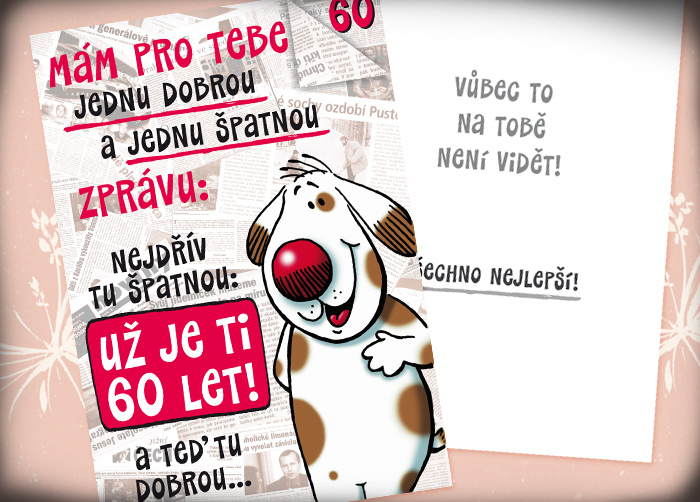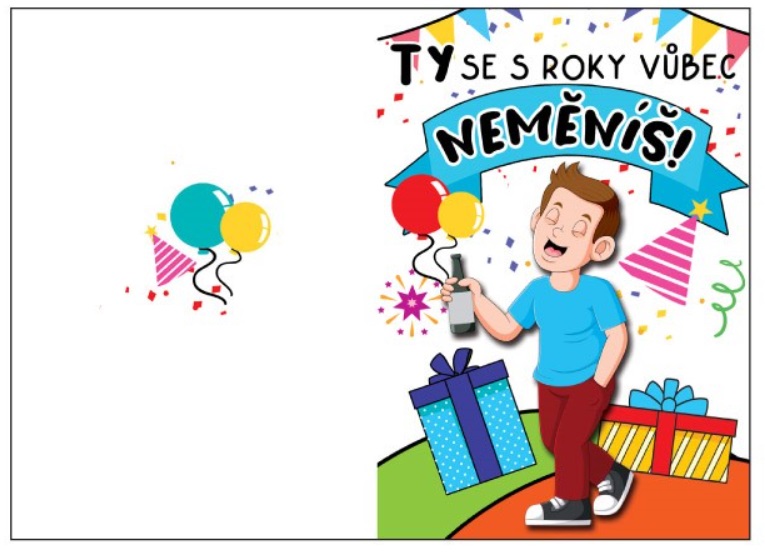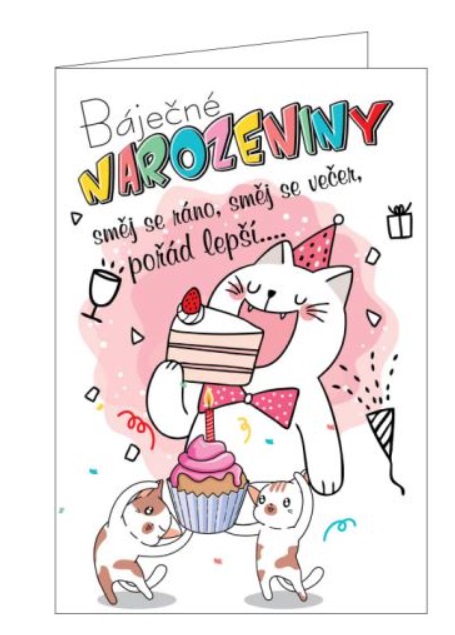Dárková karta - milión - narozeniny 2 -Dřevěný svět online - Největší český výrobce doplňků | Překližková dna a víka s potiskem | Výřezy z překližky | Macramé | Bobbiny

Solve Přání k narozeninám 77maruska77 (Birthday wishes 77maruska77) jigsaw puzzle online with 12 pieces

Rukodělný kroužek a ruční práce *online* - Papírové přání k narozeninám, ke dni matek, k Valentýnu - YouTube
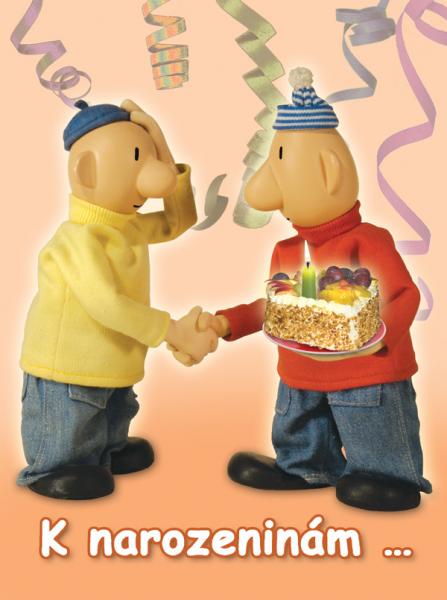
Elektronické pohlednice a obrázky k Narozeninám | strana-1 | Textová přáníčka, blahopřáníčka a citáty | www.blahopranicka.cz

Elektronické pohlednice a obrázky k Narozeninám | strana-1 | Textová přáníčka, blahopřáníčka a citáty | www.blahopranicka.cz